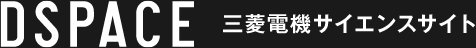H3ロケット3号機打ち上げへ—成功を支える「縁の下の力持ち」の想い

2月のH3ロケット試験機2号機打ち上げ成功から約4か月。H3ロケットがいよいよ本格的に衛星打ち上げを始動する。6月30日(日)、H3ロケット3号機は先進レーダ衛星「だいち4号」打ち上げに挑む。
新型ロケット発射、となるとどうしてもロケットエンジニアがフォーカスされがちだが、当然ながらロケット打ち上げ成功には、多くの関係者の努力が欠かせない。ロケットは巨大システムであり、多くの人たちが思いを一つにして尽力することが成功の鍵なのだ。
実は昨年2月半ば、H3試験機1号機打ち上げ取材に入った種子島宇宙センターで、ロケット打ち上げを支える現場の「縁の下の力持ち」の声を聴きたいとJAXA広報部にお願いした。急遽アレンジ頂き、2月16日にJAXA職員3人の方々が取材に応じて下さった。種子島宇宙センタ―に勤務し、打上げ管制隊・総務班で活躍した清水萌さん、麻生悠太さん(麻生さんは地元・種子島出身)。広報班として種子島のプレスセンターに詰め、衛星系技術解説員を務めた小野温さんだ。

試験機1号機失敗のため掲載を見送ったが、3号機打ち上げに向けてやっと紹介できる。ロケット打ち上げを支える方たちの想いは今回も熱く燃えているはず。その真摯な想いをぜひお読み下さい。
打ち上げ時の音の計測も仕事のうち
- —お仕事内容を教えて頂けますか?
-
清水萌さん(以下、清水):
打上げ管制隊では総務班に所属します。総務班は大きく分けて地元の対策と環境の整備があります。例えばロケットの打ち上げ時には結構大きな音がするのですが、周辺の集落でどのくらいの大きさの音になるかの計測の手続きをします。また今日はこれからロケットの機体移動がありますが、一般の方に事故などがないよう、警備員の手配をしたりします。

- —音を計測するんですね!
-
清水:
音響計測はこれまでのロケットでもやっていました。H3で久しぶりに新しいロケットになるので、筑波から環境試験技術ユニットさんに来てもらって本格的に行います。
- —結果が気になります。麻生さん、お仕事についてお願いします。
-
麻生悠太さん(以下、麻生):
地元でご協力頂いている関係機関、周辺住民の方に打ち上げや燃焼試験の計画、規制等をお知らせするのが主な仕事です。誤って規制区域に入ってしまうことなどがないように、ご協力をお願いしています。

- —お二人は種子島ご出身だったりしますか?
-
麻生:
自分、種子島です。
- —宇宙に憧れてJAXAに入ったんですか?
-
麻生:
ロケット打ち上げは小さい頃からよく見ていましたが、自分がロケット関係で働くことはあまり想像したことがなかった。島から離れて「ロケットすごいよね、いつも見られていいね」と言われて初めて、今まで当たり前に思っていたことがすごいことなんだなと感じたこともあり、JAXAに入ることになりました。
- —そうでしたか。後で詳しくまた聞かせて下さい。小野さんは衛星の技術解説員ということですが、ふだんはどんなお仕事をなさっておられますか?
-
小野温さん(以下、小野):
ふだんはGOSAT-GW(温室効果ガス・水循環観測技術衛星)プロジェクトで、ユーザとの調整や衛星の観測データ処理に携わっています。ここ種子島では竹崎展望台内のプレスセンターでALOS-3(だいち3号)の技術解説員として、記者さんから質問があった場合に対応しています。

- —なるほど、GOSAT-GWはH-IIAロケットで打ち上げ予定ですものね。
大変だったこと—JAXA職員も宿がとれない!

- —久しぶりの新型ロケット打ち上げ。大変だったことはなんでしょうか。
-
清水:
出張者から宿がなかなか取れないという話がありました。基本的には自分で宿をとってもらっていますが、それでもとれない方を総務班で部分的に支援したりして、想定外に大変でした。
- —私たち取材者も苦労しましたが、JAXAの方も!あらかじめ抑えたりはしないんですか?
-
清水:
そうですね。職員から支援依頼があったときには、総務班のみんなで手分けして電話したりしています。
- —宿問題は本当に悩ましいですね。麻生さんは何が大変でしたか?
-
麻生:
地元の方々への説明では、いつもだと年度初めぐらいにロケット打ち上げ計画を説明します。ここ最近はH3ロケットの計画がなかなか見えてこなかったこともあり、地元の皆さんへの説明がいつもより遅くなり、なかなか説明ができなくて「いつ(ロケットは)上がるんだ」と心配の声を頂いたこともありました。
- —それは大変ですね。印象に残ることは何かありました?
-
小野:
打ち上げが延期になった時です。延期の情報をプレスリリースに載せた瞬間から種子島のプレスセンターの電話が鳴り止まない。その電話に対して、対記者さんということもあり、正確に伝えないといけない。普段私が行っている衛星プロジェクトの業務とはまた違った緊迫感を感じました。
- —同じ地球観測衛星でもGOSAT-GWとだいち3号は目的が異なりますよね。
-
小野:
おっしゃる通りミッションが違いますね。GOSAT-GWという衛星は、異なる2つのセンサが同時搭載されていて、地球温暖化の原因とも考えられている温室効果ガスと、地球上の水循環を観測する衛星です。一方でだいち3号は災害対応をミッションとした衛星です。共通点としては両衛星ともにわたしたちが住む地球を観測する衛星ですので、社会貢献という観点で重要なミッションを担う衛星と考えています。
- —清水さんにとって印象的だったことは?
-
清水:
2022年11月にH3ロケットの最終段階の試験、CFT(1段実機型タンクステージ燃焼試験)がありました。

-
清水:
本番の打ち上げさながらに機体移動の警備とかもやりました。種子島の射点でロケットが燃焼するのを見たのは初めてで、「あとは飛び立つだけだ」と感慨深いところがありましたし、本番に向けての想定もできました。
-
麻生:
印象に残っていることでは、種子島宇宙開発促進協議会や南種子町宇宙開発推進協力会がH3ロケット用に新しくのぼりを作成して下さったり、見学客の方に差し上げるバッジやクリアファイルを作って下さったりしたことです。種子島内一市二町の首長やさまざまな団体さんにより構成されている組織で、日頃から多大なるご協力を頂いていますが、今回さらに盛り上げて下さっていることを、いつも以上に感じました。

- —私も見ました!あのかっこいいのぼりですね。麻生さんは地元採用ということですが、小さい頃から打ち上げを見ていらしたんですか?
-
麻生:
はい。家の縁側から見ていました。
-
小野:
すごい!初めて種子島出身のJAXA職員の方に会いました。
- —種子島出身の正社員の方はあまりいらっしゃらないんですか?
-
麻生:
近い年代ではあまりいないと聞いたことがあります。自分はJAXAの事務系でキャリア採用の枠で試験を受けて入社しました。
- —小さい時に見ていた打ち上げと、今JAXA職員として見る打ち上げは違いますか?
-
麻生:
全然違います。今までは「あ、上がってるな~」ぐらいの感じでしたが、自分が関わる今は「無事に上がりますように」と緊張しながら見ています。
-
小野:
衛星開発メンバーは、結構ベテランの方でも打ち上げを見ていない方もいらっしゃるので、頻繁にみられるのは羨ましいです。
- —そうですよね。麻生さんは地元との調整も適役ですよね。
-
麻生:
前から知っている方々も中にはいらっしゃるので、会話しやすかったりという面はありますね。
打ち上げに向けて
- —打ち上げに向けた期待や抱負をお願いします。
-
小野:
ロケットと衛星とでプロジェクトこそ違うものの、関係する多くの人々が労力をかけて進めています。だいち3号のキーとなる光学系の大型化実現などのセンサ技術が、今後の衛星開発の高度化に貢献することを期待したいです。
-
清水:
私たちの活動は見えにくいですが、地元関係機関のみなさんとの信頼関係を保ち、職員が気持ちよく働けるように環境を整備することで確実な打上げに貢献したい。最後の最後まで自分の職務を全うしたいと思います。
-
麻生:
地元の方々にもすごく期待してもらっていると思います。喜んでもらえるよう、「無事に打ちあがりました」と報告ができるようになればいいなと思っています。
2023年の打ち上げは成功には至らなかったが、原因究明を迅速に行い、2024年2月17日、H3ロケット試験機2号機は見事に打ち上げ成功を果たした。それも清水さん、麻生さん、小野さんをはじめたくさんの縁の下の力持ちの方々の、たゆまぬ努力の賜物だろう。だいち3号のリベンジを4号で果たしてほしいと切に願う。
ロケット打ち上げ見学するための必勝テク

人生で一度は体験してほしいと思うのが、ロケット打ち上げ見学だ。その光、音、振動を全身で体験すれば、ロケットが飛び立つためにどれほど莫大なエネルギーが必要か、同時にそのエネルギーを正確に制御することの大変さと人間の力の凄まじさを、言葉抜きに体感することができる。
だが、現在、種子島での打ち上げ見学は困難を極めるのが実情だ。まず座談会で語られているように宿の絶対数が少ない。そして足となるレンタカーの確保が厳しい。種子島の玄関である空港や西之表港と発射見学場のある南種子町を結ぶバスが2023年3月末で廃止、4月1日からは予約制乗り合いタクシーが導入された。高速船や航空便の発着に合わせてそれぞれ1日最大4便、土日祝日も運行する。前日までに電話予約が必要だ(欄外リンク参照)。
発射見学場で出会った人たちには、宿がとれずテント持参の方も多かった。南種子町に4か所ある公式見学場のうち、テントを張ることができるのは宇宙が丘公園。そしてレンタカーを確保できなかった方の中には、鹿児島や隣の屋久島でレンタカーを借りてカーフェリーで種子島入りする方もいた。

宿について、種子島を昨年4回、合計約10回訪れた私の経験では、ネットで検索できる宿は満員のことが多い(キャンセル料がかかる直前に空きがでることも)。南種子町や中種子町のウェブサイトの宿泊情報に出ている民宿に電話をしたり、Googleマップの種子島で宿泊と入力して出てくる宿に順番に電話して、かつて宿を営んでおられたお宅に泊めて頂いたこともある。レンタカーも同町のウェブに紹介されている地元のところがねらい目。種子島自動車学校も軽トラ・軽自動車を貸し出している。
苦労して種子島にわたっても、打ち上げが延期になる可能性も残念ながらある。それでもぜひ、ロケット打ち上げを体感する価値があると言いたい。その轟音と光から、人間の力の結集の凄まじさが感じられるはずだから。
- ※
本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。