 和食シリーズ企画第3弾
和食シリーズ企画第3弾
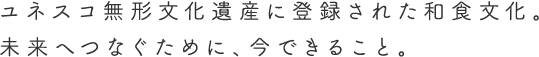
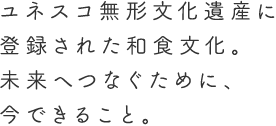
第16回 鰻
養殖鰻のその先に
鰻の未来はあるはず
日本橋いづもや三代目
岩本公宏さん
創業から70年以上に渡り、鰻を焼き続けてきた「日本橋いづもや」。
3代目の岩本公宏さんは、江戸時代初頭の「蒲(がま)の穂焼き」などを現代に復活させ、
鰻食という食文化を踏まえて、焼き台に向き合い続けています。
蒲焼き以前から愛され続ける鰻の魅力について伺いました。
鰻の“旬”は土用ではなかった

- 編集部
- 鰻の蒲焼きと言えば、「土用」には欠かせない、季節の風物詩です。もっとも夏の盛りに鰻を食べるようになったのは、江戸時代中期以降と言われていますよね。
- 岩本さん
(以下、敬称略) - 「夏場に売れ行きの悪い鰻屋から相談を受けた、平賀源内が『本日丑の日』と貼り出したところ、その店が繁盛した」という説はよく聞かれますよね。そのほか、大田南畝(おおたなんぽ)こと蜀山人(しょくさんじん)が「丑の日に鰻を食べると薬になる」と喧伝したという説もあります。
- 編集部
- 真相は藪の中……というところでしょうか。そもそも鰻の旬が夏の土用かと言うと……。
- 岩本
- 違いますよね。天然鰻の“旬”は冬眠に入る前の晩秋から初冬にかけて。本来、「土用」に象徴される夏場は脂が乗らず、食味が落ちる時期です。もっともいまでは養殖の技術が進んだので、季節による味の差はあまりなくなりました。あるとすれば、5~6月に出てくる「新仔(シンコ)」でしょうか。骨もほとんど感じないほどやわらかく、さっぱりした味わいでタレの味がしみやすい。いわゆる「はしり」の味ですね。
江戸後期に生まれた蒲焼きと丼が鰻の運命を変えた
 蒲の穂焼き
蒲の穂焼き- 編集部
- 鰻は日本人にとって鯛などと並んで、もっともつき合いの長い食用魚のひとつと言われています。
- 岩本
- 5000年以上前の貝塚からも鰻の骨が発見されています。7~8世紀にかけて編纂された「万葉集」にも、「夏ヤセに鰻がいい」と歌われています。蒲焼きの登場は14世紀ですね。ただし、現在のような開いたものではなく、筒切りにした鰻を串に刺して焼いた「蒲の穂焼き」と言われる形のものです。
- 編集部
- 岩本さんが再現された品です。
- 岩本
- 再現といっても、当時は詳しいレシピもない頃ですから、試行錯誤を繰り返しました。店で出す以上は、現代人が食べてもおいしいと思えるような工夫を凝らさなければなりません。切って焼いて塩を振るだけではおいしく召し上がっていただけませんから、ちょっとした工夫を凝らしてあります。企業秘密ですが(笑)。
- 編集部
- 現在のように身を開いた鰻を、甘辛い醤油ダレを塗った蒲焼きの登場はまだ先の話ですね。

- 岩本
- 「開く」というのがひとつの転機でしょう。戦国時代に隆盛を極めた刀鍛冶が、天下太平の江戸時代になって、刀剣ではなく生活のための道具をつくるようになった。町人文化が花開く文化文政年間(1804~1830年)、いわゆる「化政文化」の頃に出刃包丁や菜切包丁など多様な包丁が登場しています。この頃、蒲焼きも身を開いて甘辛い醤油ダレで焼くようになっていきました。
- 編集部
- 「うな丼」を始めとしたどんぶり飯が生まれたのもこの頃だと言われています。「日本橋いづもや」では「うな重」の注文が多いとは思いますが…。
- 岩本
- まず「丼」から始まったというのは間違いないようです。「重」は江戸後期説や明治・大正説などいくつかあるようですが、はっきりしたことはわかってい ません。「丼」と「重」は単純にうつわの違いです。どんぶり飯をかっこむのと、お重から一口分ずつ箸で食べるのとで味わいは変わるかもしれませんが、基本的に鰻の質に違いはありません。さらに言えば「うな重」の「並」「上」「特上」も、質の違いではありません。並は鰻が少なく、特上は鰻の量が多い。つまり鰻の質の違いではなく、量の違いということがほとんどです。
- 編集部
- 開き方も関東と関西で異なりますし、関東では「蒸す」という工程も入ります。
- 岩本
- やはり最大の違いは「蒸し」の工程でしょう。うちも江戸前の鰻屋ですから、割いて串を打ってから白(しら)を入れ(生の鰻を素焼きすること)、そこで20分程度蒸し上げます。そうすることで余分な脂が落ち、タレも乗りやすくなる。素人では持てないほど柔らかくなった鰻を我々は手早くタレにつけて何枚も同時に炭の上で焼いていくわけですね。ちょっとご覧になりますか?
- 編集部
- ぜひお願いします!
プロに聞く、家でおいしい鰻を食べる方法


- 岩本
- 特に昼と夜のピークタイムは戦場です。注文を受けてから鰻をさばいたのでは到底間に合いません。そこでお客様の入り時間から逆算して仕込みを始めます。白焼き、蒸しなどの工程を経て、仕上げにタレにくぐらせながら3回ほど焼いてお出しします。
- 編集部
- 色つけ(蒸し上がった鰻をタレにくぐらせて蒲焼きに仕上げる作業)時の火は強くないんですね。それにうちわも、たまにゆーったりとあおぐくらい。
- 岩本
- 仕上げの段階では、タレを身に定着させるのが目的ですから。鰻の身って脂が多いからどうしてもタレをはじいてしまう。だから二度三度とタレにくぐらせて、その都度火にかけるんです。確かに一定の香ばしさもつけたいんですが、火が強いとその前に焦げてしまいます。焼き目はしっかりつけますが、焦げ目は雑味になる。一方、最初の白焼き――われわれは「白入れ」と呼んでいますが、その段階では紀州備長炭の火力を強くして、表面に一気に火を入れます。仕上げではむしろ空気を揺らして温度をコントロールすることが目的になるわけです。
- 編集部
- 一言で「焼く」と言っても、さまざまな狙いがあるんですね。焼く場所もずいぶん細かく移動させています。
- 岩本
- どうしても炭火だと温度のムラが生じてしまう。うちわでコントロールしながら、より均一に火に当たるよう場所を調整するんです。そろそろいいですかね。さあ、これで焼き上がりです!
- 編集部
- これはおいしそうです! ちなみにスーパーで買ってきた鰻の蒲焼きをおいしくする方法はありますか?
- 岩本
- まず鰻の身についたタレが生臭かったり、味がいまひとつということが多いので、ぬるま湯で洗います。その鰻をペットボトルの緑茶で煮ます。お茶で煮ると、鰻がやわらかくなり、臭いも気にならなくなる。数分間煮たら鰻を引き上げ、オーブントースターでタレを2~3回にわけて塗りながら焼いてください。タレは、醤油と煮きったみりんを同量にするのが基本ですが、塩気と甘さのバランスは調節してください。好みの味に寄せることができるのも、市販の鰻を家庭で調理するメリットのひとつですね。
- 編集部
- もうひとつ。スーパーや店頭でいい鰻を見分ける方法はあるのでしょうか。
- 岩本
- あります。鰻の味は値段と比例するんですよ。国産でもどこの国のものでも、きちんと鰻を育てると、どうしたって高くつく。安い食品にはそれなりの理由があるはずなんです。まじめな生産者を支援することにもなるので、少し高いと感じてもそちらを選んでいただきたいですね。
完全養殖の先にある鰻の未来
- 編集部
- そういえば「いづもや」という屋号、関西ではときどき見かけますが、関東ではあまり見かけません。
- 岩本
- もともと大阪に多い屋号みたいですね。明治の頃、大阪に「いづもや」は300軒ほどあったようです。当時の最上の鰻は宍道湖のもの。出雲市と松江市にまたがる宍道湖は、淡水と海水が混ざった汽水湖ですから栄養も豊富で、鰻の味もすこぶる良かったと考えられます。それで当時の人々は鰻を扱う店を始めるとき、産地の「出雲」にあやかったのでしょう。当時は約一週間かけて一大消費地である大阪まで運ぶための「鰻街道」も整備され、要所には鰻を弱らせないよう、泳がせるための「鰻池」も造られたそうです。

- 編集部
- それほど大阪では鰻が人気だった、と。
- 岩本
- その大阪に先代が修業に行っていたから、うちは「いづもや」なんです。創業は1946年(昭和21年)としておりますが、実はその4年前の1942年(昭和17年)に神田・美倉橋のガード下で始めたそうで、当時は鰻と焼鳥の二本柱で商売をしていたそうです。第二次世界大戦で東京は焼け野原になりましたが、終戦して間もなくバラックを建てて、営業を再開したそうです。
- 編集部
- 「日本橋いづもや」では通常の蒲焼きに加えて、岩本さんが再現された「蒲の穂焼き」、生醤油で焼いた「生醤油焼き」や、独自開発した鰻の魚醤を蒸した鰻につけて焼き上げた「いづも焼き」なども品書きにあります。こうした他にない品は昔から提供されていたんでしょうか。
- 岩本
- いえ、僕の代になってからです。鰻って昔もいまもごちそうですよね。これほどまでに日本人を惹きつける、蒲焼きやうな重はとても完成度の高い日本食だと言えます。しかし縄文時代から数えて5000年以上、江戸時代に蒲焼きやうな丼が登場してからでも200年が経過しています。先人の教えを守り、受け継ぐだけではなく、新しい味を生み出し、次の世代に渡すのが私たちの役割だと考えています。
- 編集部
- 次世代に鰻のバトンを渡す話となると、漁獲量減や資源管理などの話題を避けては通れません。
 白焼き
白焼き

- 岩本
- そうなんです。今のまま何もしなければ、鰻を食べる文化そのものがなくなってしまうかもしれない。現在の鰻の流通量の7~8割がスーパーやコンビニ、フランチャイズ飲食店の加工鰻で、われわれ專門店は2~3割を使用しています。その比率はさておいても、漁獲減や資源管理問題は鰻に関わる仕事をするすべての者が考えなければならない話です。

- 編集部
- いま岩本さんは、鰻という日本食の未来をどう考えていますか。
- 岩本
- 理想は受精卵の人工ふ化→成魚の鰻に育成→人工授精までを人工飼育で完結させる完全養殖でしょう。実は、すでに技術的には可能なところまで来ています。ただし、現状では、一人前のうな重がとんでもなく高額になってしまう。研究のスピードを上げ、それまでの間、いかに乱獲を防ぐか。いまや我々もこうした問題から目を避けてはいられないと考えています。
取材・文/松浦達也 撮影/魚本勝之
2018.02.06
