皆さんもさぞかし、2月末のこのニュースには驚いたのではなかろうか。冥王星騒動で、太陽系の惑星は8つで落ち着いた、太陽系は果てまでわかってしまったと思っている方がいるかもしれないが、なかなかどうして太陽系はまだまだ先が見えていないのである。
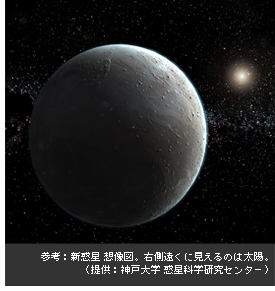 今回の研究は、神戸大学で研究しているブラジル人パトリック・リカフィカ氏と向井正氏によるものである。もともと、私自身が太陽系の研究者なので、リカフィカ氏が大学院の頃から私は彼の研究をよく知っていた。彼は理論家として、太陽系外縁部にある外縁天体(エッジワース・カイパー・ベルト天体)の軌道の理論的な研究を行っていた。太陽系外縁天体とは、海王星の外側を回る天体群である。1992年に最初の一つが発見されてから、その数はすでに1000個以上にのぼっている。そして、それらの天体の軌道の分布に特徴的な性質がある。通常の惑星がまわる黄道面に対して、傾いているものが多いのである。冥王星は17度も傾いているし、冥王星よりも大きなエリスになると、44度にも及ぶのである。さらに真円ではなく、大きくゆがんだ楕円軌道のものもある。軌道のゆがみ具合を専門用語では「離心率」と呼ぶのだが、これが飛び抜けて大きく、非常に大きな軌道を持ち、周期が千年を超えるものさえあるほどだ。通常の惑星形成理論から考えると、このような傾きと離心率を持つためには、何らかの重力的な擾乱が必要なのだが、これまで、こうした特徴をすべて統一的に説明できるモデルは皆無といってよかった。
今回の研究は、神戸大学で研究しているブラジル人パトリック・リカフィカ氏と向井正氏によるものである。もともと、私自身が太陽系の研究者なので、リカフィカ氏が大学院の頃から私は彼の研究をよく知っていた。彼は理論家として、太陽系外縁部にある外縁天体(エッジワース・カイパー・ベルト天体)の軌道の理論的な研究を行っていた。太陽系外縁天体とは、海王星の外側を回る天体群である。1992年に最初の一つが発見されてから、その数はすでに1000個以上にのぼっている。そして、それらの天体の軌道の分布に特徴的な性質がある。通常の惑星がまわる黄道面に対して、傾いているものが多いのである。冥王星は17度も傾いているし、冥王星よりも大きなエリスになると、44度にも及ぶのである。さらに真円ではなく、大きくゆがんだ楕円軌道のものもある。軌道のゆがみ具合を専門用語では「離心率」と呼ぶのだが、これが飛び抜けて大きく、非常に大きな軌道を持ち、周期が千年を超えるものさえあるほどだ。通常の惑星形成理論から考えると、このような傾きと離心率を持つためには、何らかの重力的な擾乱が必要なのだが、これまで、こうした特徴をすべて統一的に説明できるモデルは皆無といってよかった。
リカフィカ氏は、大学院生の頃から、こういった太陽系外縁天体の軌道の特徴を一つ一つ丹念に調べ、数値シミュレーションによって、どんな原因でどのような特徴が説明できるのかを綿密に研究していた。筆者は、その経過を聞かされるたびに、「おぉ、ずいぶんと進んでいるなぁ」と思っていた。そんな中、博士論文をまとめおえたリカフィカ氏が、ある研究会でついに一つの結論に達したことを発表したのである。
それは、「太陽系外縁天体の観測された軌道分布の特徴をすべて矛盾なく再現できる原因がひとつだけある。それは未知の惑星クラスの天体の存在を仮定することである」というものであった。これには驚いた。それまで火星サイズの天体が存在するはず、と主張した人はいたのだが、太陽系外縁天体の軌道の性質のごく一部しか説明できないものであったし、われわれ研究者の中にも、すでにそういった可能性はないかもしれない、と考え始めていたからだ。
リカフィカ氏に、さっそく論文原稿を送ってもらった。タイトルは"An outer planet beyond Plutoand origin of the trans-Neptunian belt architecture" とある。未知の惑星クラスの天体の質量は、地球の0.3から0.7倍程度、軌道は、近日点距離が80天文単位 (1天文単位とは地球と太陽の平均距離で、約1億5千万キロメートル) 以上、軌道は大きく、その長半径は100-175天文単位、軌道面の傾斜角は20-40度である。この惑星が太陽に近い場所にあれば、その明るさは14.8-17.3等級と考えられ、現在計画されている大規模サーベイ観測が始まれば、いくぶん遠くにあっても発見の可能性は十分にある。そして、この論文が審査を通過し、4月にアメリカの天文学会誌に掲載が決まった時点で、彼らと連絡を取り、記者会見を2月27日に国立天文台で開催したのである。(国立天文台広報室は、国立天文台の研究者の成果だけでなく、こうして関連分野の研究者の成果を世に問うお手伝いもする、いわば天文学そのものの広報でのナショナルセンターとしての役割を果たしている。)
その反響があまりに大きかったために、神戸大学でも改めて記者会見を開くことになったそうである。いずれにしろ、宇宙はまだまだ見えていない。現在の太陽系でさえ、まだ何があるのかわからない。そして、この惑星クラスの天体が発見されれば、新しい惑星に認めるかどうか(※)、再び議論が始まることだろう。
※ 2006年に定められた惑星の定義については拙著「新しい太陽系」(新潮新書)を参照のこと。本発表の内容の詳細は、神戸大学のホームページを参照のこと。
http://www.org.kobe-u.ac.jp/cps/press080228_j.html
|
