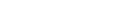Vol.5
生命のサイズを決めているものは何か?
今回と次回のコラムでは、皆さんからいただいたテーマや疑問に、僕なりに答えてみたい。今回は、次の2つの疑問について考えてみよう。
—宇宙の生命は目に見える体を持つのか。意識だけで存在している可能性は?
—素粒子並みに小さい生命体がいる可能性は?
これらの疑問はそれぞれ別の方から寄せられたものだが、その根底となる問いは共通しているように思われる。つまり、宇宙においても生命は、ある大きさを持つ物質でできているのか、という問いである。生命は一体どこまで小さくなることができるのだろう。生命のサイズを決めているものは何であろうか。
この問いに答えるためには、生命とは何か、という究極の問いから考えてみる必要がありそうだ。生命というものだけが持つ“生きている”という特徴とは、いったい何であろう。
生きているということ
生命とは何であろう。改めて、これほど答えにくい問いはないと気づかされる。
まず生命は、ある一定の環境に置かれたとき、何かの活動をしつづけることができる。周囲から水や空気や食べ物といった物質を体内に取り入れたり、何かを排出したり、運動をしたり、増殖したり、あるいは思考したりという活動を続けることができる。僕らは、生命が宿る物質がそのような振る舞いをするときに、それが“生きている”と認識する。
反対に、生命でない単なる物質が、同じように一定の環境に急に置かれたとしよう。非生命物質は、最初は何かしらの運動をしているかもしれないが、その運動は急速に止んでしまう。持っていた運動エネルギーは、周囲の空気や水などとの摩擦によって失われる。河原で投げた小石の運動がすぐに止まってしまうように、何も起きない状態 — 熱力学平衡状態と呼ばれる安定な状態に短時間で達する。
運動だけではない。生命が宿らない物質は、徐々に安定な別の物質へと変化していく。例えば、空気中に置かれた鉄が徐々に錆びていくように、ゆっくりと、しかし確実に、安定な物質へと変化していく。安定な物質は自力で元に戻ることはない。覆水は盆に返らないし、錆びた鉄は勝手に金属に戻ることはない。熱力学平衡状態とは、自力で動けない、変われない、死の状態といってよい。
一方、生命をつくる物質も、安定な物質へと、ゆっくりではあるが同様に変化しようとする。生命は、自分の体を作る物質が別の物質になる前に、これらを自ら分解し、周辺の環境にある新しい原子を取り込んで、自分の体を絶えず作り変えている。代謝と呼ばれる活動である。
皆さんも数年前と見た目はさほど変わらないかもしれないが、原子レベルで見れば、体を作るほとんどの原子は入れ替わってしまっている。生命は自分自身を作り変え、環境と物質をやり取りすることで、熱力学平衡状態に陥ることから免れている。
物質無くして生命無し?
これら生命の振る舞い — 僕らが“生きている”と認識できる振る舞いを担っているのが、生命を作る“機能をもつ物質”である。運動、増殖、代謝、さらには思考さえも、それを担当する機能をもつ物質が行っており、これら無くしては生命の振る舞い自体が生じない。僕ら地球生命の場合、これらの物質とは、タンパク質であったり、DNAであったり、脂質であったりする。
僕らは自分の意識を、物質とは無縁の実体のないものと思いがちだ。しかし、僕らの意識も実体のないものでは決してない。
記憶や思考といった意識とは、僕らの脳内のニューロンという細胞が連結したネットワーク内で起きている化学反応に過ぎない。人工知能 ― AIでさえ、コンピュータ内の電子基板におけるニューロンのネットワークのような仕組みで生じる電気信号が生み出したものに過ぎない。
僕らが“生きている”と認識できる振る舞いを担っているのが、これら機能を持つ物質である。そうである以上、現状では、僕らが認識できる生命とは、人工知能などの無機物を含めたとしても、物質でできている範疇に限られる。
逆に、僕らが認識できない生命は、もしいるならば、僕らが“生きている”と認識する振る舞いをすることはなく、したがって、「生命」という言葉ではなく、何か別の言葉で語られるべきだろう。“生きている”と僕らが認識できることが生命と非生命をわける要素であれば、生命とは何かという問いや、認識できないものをどう定義するかという問いは、科学だけでなく、哲学にまでまたがる問いであろう。
原子はなぜ小さいのか
さて、ここでは単純に、僕らが“生きている”と認識できる生命を考えていこう。機能をもつ物質でできた生命は、どこまで小さくなることができるのだろうか。一般法則はあるのだろうか。
この問いに正面から答えようとしたのは、物理学者エルヴィン・シュレディンガーである。
20世紀初頭に量子力学の基礎を創ったシュレディンガーは、その業績により1933年にノーベル物理学賞を受賞している。現在、理系大学生の何割かが、大学の物理学の講義で最初に挫折するのが、有名なシュレディンガー方程式であり、20世紀以降、多くの学生にトラウマを植え付けた。果たして僕もその例外ではない。
シュレディンガーは、1944年に出版された著書「生命とは何か」において、次のような問いを発している。
原子はなぜそんなに小さいのか、と。
僕らは日常的に、自らを構成する原子を意識することはない。原子は直接目に見えなければ、これを触った感触もない。地球上に生きる最小サイズの生命である細菌にとっても、それは同じである。細菌一個体あたりにさえ、およそ100億個という途方もない数の原子が含まれるのだ。タンパク質やDNAなど、機能をもつ物質一つとっても、膨大な数の原子が含まれている。
生命をどこまで小さくできるかという問いは、機能をもつ物質をどこまで小さくできるかという問いと同じだといってよい。なぜなら、仮に機能を持つ物質が非常に少ない数の原子、例えば数個あるいは一個の原子からなるとすれば、生命自体も限りなく小さくできるからだ。しかし、その場合、どんな不都合が生じるだろう。

なぜ生命は原子と比べてこんなに大きいのか
機能をもつ物質の周囲には、必ず別の分子が存在する。細胞内であれば水分子、空気中であれば窒素や酸素の分子などが存在する。原子レベルでみると、これら分子は様々なスピードで、乱雑に自由に動き回っている。熱運動と呼ばれるものである。今、この瞬間にも、僕らの指先にも、顔にも、体中いたるところに無数の窒素や酸素の分子が高速でぶつかっている。ただ、僕らの体が大きいがために、一つ一つの分子の衝突を感じることはない。
もし、機能をもつ物質が数個、あるいは一個の原子からなる場合、どうであろう。周囲の分子と機能をもつ物質とが同程度の大きさである以上、分子の熱運動により大きな影響を受ける。
例えば、ニューロンが数個の原子でできている場合、周囲の分子が偶然に高速で衝突することによって勝手に化学反応が生じてしまう。すると、何かしらの思考が偶発的に発せられ、もはや秩序だった意識はもてないだろう。また、代謝を担うタンパク質が少数の原子から成るのであれば、これが周囲の分子の衝突によって、別の形状に変わってしまうこともおきうる。そうなれば、代謝を維持することは困難であり、生命は短時間で熱力学平衡状態に陥ってしまうだろう。
シュレディンガーの、原子はなぜそんなに小さいのか、という問いは、本当はこういう問いであるべきである。
すなわち、なぜ生命の体は原子に比べてこんなにも大きいのか、と。
そして、シュレディンガーは、著書「生命とは何か」の中で、その答えをこう述べている。
「生命および生命が営むあらゆる過程はきわめて多くの原子から成る構造をもっていなければならない。そして、偶発的な一原子による出来事が過大な役割を演じないように保障されていなければならない。」
生命のからくり
機能をもつ物質は、周囲の分子の影響でどこかに不具合が生じても、その機能を失わない程度に大きな物質である必要がある。そして時間が経てば、不具合が生じた箇所も、そうでない箇所も、代謝によって、全て新しい物質へと作り変えられる。
「素粒子並みに小さい生命はいるの?」と問われると、素粒子はおろか少数の原子から成るような生命でさえ、現実的には存在しないだろうということになる。統計力学をご存知の読者がいれば、生命や機能をもつ物質は、必ず巨視的な集団でなければならないとも言い換えられる。
20世紀、統計力学を含む物理学は、宇宙で普遍的に通用することが明らかになった。そうであれば、この生命のサイズに関する議論も、この宇宙において普遍的なものであろう。
では、最低どのくらい多くの原子が集まれば、生命 —“生きている”と認識できる物質— を構成しうるのか。シュレディンガーは、これについても、100万から1000万程度の原子の集団だろうと考察している(興味をお持ちの方は、著書「生命とは何か」をお読みいただくとよい)。
彼の予言したこの数は、細菌一個体を構成する原子の数である100億個より少ないものの、新型コロナウイルスを含む、一般的なウイルスを構成する原子数の1000万程度と符合する。もっとも、科学者のなかでも、ウイルスが“生命”であるか、統一的な“認識”はないのだが。

ここまで、生命を作る機能をもつ物質は、変化しないために多数の原子からなる必要があると述べてきたが、例外もある。
それは、増殖や遺伝の役割を担うDNAである。
DNAを構成する原子の数は、細菌では数1000万、人間の細胞では数100億ともいわれる。巨大な原子の集団である。ただし、DNAを構成する塩基対と呼ばれる一つのユニットの原子数は数10程度と少ない。たった一つの塩基対に対してであれば、周囲の分子などによる偶発的な変化は起きうる。そして実は、一つの塩基対に原子レベルの変化があるだけでも、生命全体に大きな影響が及びうる。
これを生物学者は突然変異と呼ぶ。生命は突然変異することで、流転する地球環境にも適応できる種を生み出し、多様な進化を遂げてきた。新型コロナウイルスも、変異株と呼ばれる突然変異を次々と生み出している。
むしろ、地球生命は、どんなに進化しても、DNAの塩基対だけは少ない数の原子の集団に留めているのかもしれない。
何のために? おそらく、僕らがこれからも、変わり続けていくために。
- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。