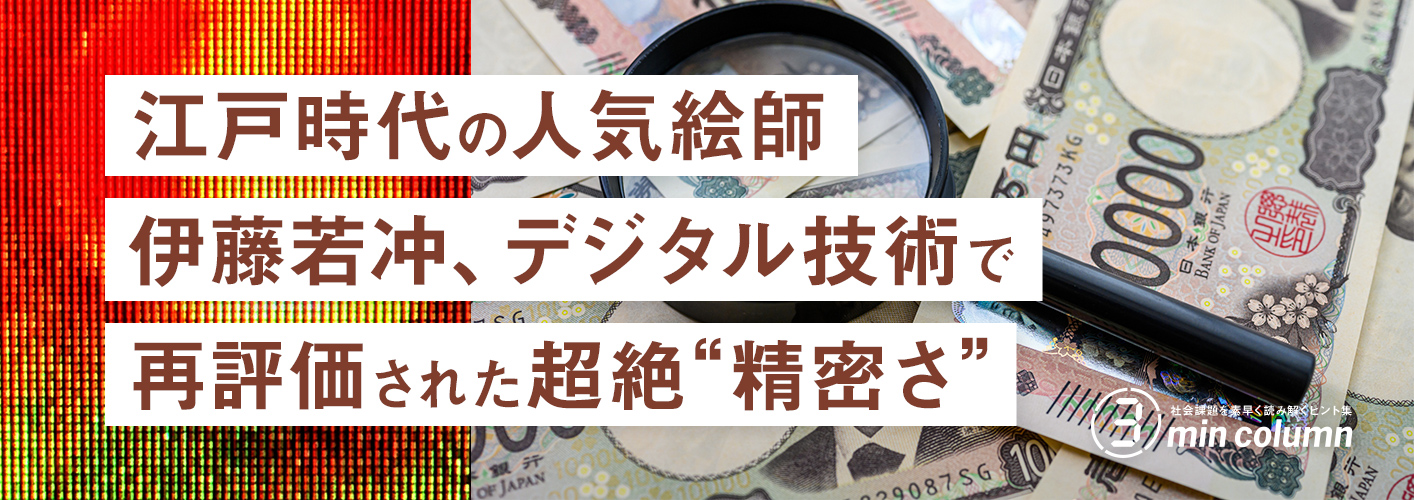羽毛の一本一本まで精密に描き上げた絵師、伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)。2000年代に入り突如としてブームを巻き起こし、その人気は未だ健在だ。2025年には、消失されたとされる若冲の幻の大作「釈迦十六羅漢図屏風」のデジタル推定復元の展示が予定され、大きな話題となっている。“精密さ”を生み出すものは何か、そして人はなぜ精密であることにこれほど惹かれるだろうか。
実は、若冲は長く一部の人々だけのものだった。現在の知名度からは考えられないが、若冲人気に火がついたきっかけとされる2000年の京都国立博物館での没後200年の若冲展のキャッチコピーは、「こんな絵かきが日本にいた」だ。
今になって急激に評価が高まった背景には、デジタル技術の進歩があるともされる。例えば若冲の鳥の羽の線はわずか0.2mm間隔。それにもかかわらず、全てが等間隔に描かれ、1本たりとも重なることはない。この恐ろしいまでの精密さは以前のテレビや印刷技術では伝えきれなかった。また、スマホの普及などで画面を拡大することに慣れ、アップにしてなお感じられる繊細な魅力にとりつかれた人も多かったのではないだろうか。色彩、構図の見事さは言うまでもないが、その細密描画を伝えるには現代の技術が必要だったのだ。「私の絵は1000年後に理解される」という謎の言葉を残したと伝えられる若冲。それはこのことを意味していたのだろうか。
若冲は多様な技法を生み出したが、その一つが「枡目書き」だ。画面全体にまず淡墨で1cm間隔に線を引き、無数の正方形を作る。この上から絵柄に合わせて淡い色を塗って下地を作り、濃い目の色で正方形に塗り込む。さらに正方形の隅には濃い色で濃淡をつける。こうしてできたマス目にさらに陰影を付けて調整していく。彼の代表作の一つである「鳥獣花木図屏風」のマス目の数は、なんと約8万6000にも及ぶ。
拡大すると無数の正方形が並ぶ姿は、デジタル画像のピクセルを思わせるが、一般的なモザイク画とは全く異なる独特のリズム感や濃密さで生み出されるタッチは、現代でも簡単には再現できない描き方だ。これこそまさに超絶技巧と言えるだろう。
そんな若冲同様、今も手作業が生み出す精密さが欠かせない“絵”が身近にある。誰もが日々触れている紙幣だ。
2024年7月に発行された日本の新紙幣、渋沢栄一らの絵柄や陰影などを表現する線幅はわずか40マイクロメートル(0.04mm)ほど。もちろん肉眼では見えない。さらに、文字幅約300マイクロメートル(0.3mm)のマイクロ文字が印刷され、コピー機では鮮明に再現することはできない。
これらは国立印刷局の専門職である工芸官により、人の手で描き出されている。まず肖像画を針の先のような細かな点を重ねて描き出す。そしてそれらを金属板に全て手作業で彫刻していくのだ。ルーペでのぞき込みながら専用の彫刻刀ビュランで彫る線は、1ミリメートル幅の中に十数本にも及ぶ。現在の工業技術で再現可能な部分もあえて手作業にすることで、偽造をさらに困難にするという。人が生み出すものには目に見えないレベルで個性があり、本人ですら再現はできない。明治以降、国立印刷局に受け継がれてきた門外不出の精密技術はこれからも継承されていくことだろう。
人が精密さを求める理由はさまざまだが、古くから人々はその限界に挑戦し、その先にある目に見えないレベルの精密さを追求し続けてきた。そして技術は進歩し、マイクロメートルからさらに1,000分の1小さなナノメートルの世界へと突入した。
精密技術が進歩した現代に若冲がいれば、いったいどんな絵を描くのだろうか。