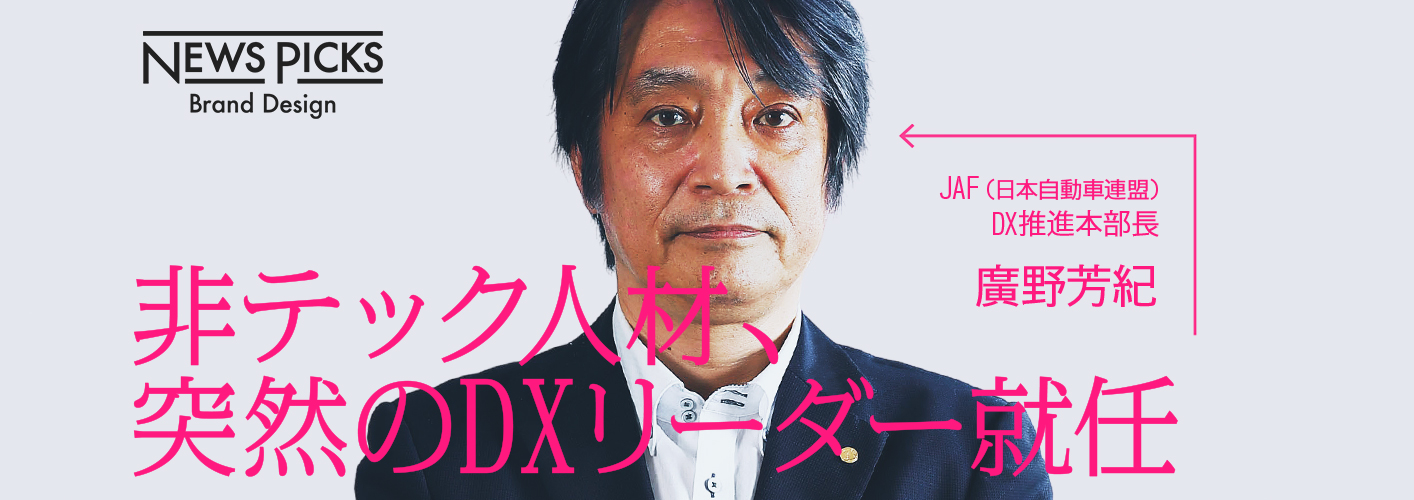前担当業務は内部監査。
非エンジニアがDX推進本部長になって大切にしたこと 

DX(Digital Transformation)を推進したいが、プロジェクトリーダーは誰が適任か、どう進めればいいか分からない……。
こう思う人も少なくないだろう。ロードサービスで知られる一般社団法人の日本自動車連盟(JAF)は2020年、DX推進本部を立ち上げ、DXに本格的に取り組み始めた。2000万人以上の会員に向けたサービス向上のために欠かせないデータの管理システム増強に挑んでいる。
このプロジェクトをリードするのが、DX推進本部長を務める廣野芳紀氏。前の担当業務は内部監査で、テクノロジーに対する見識はほぼない。一見すると、かなり思い切った人事のようだが、プロジェクトが順調に進んでいるという。廣野氏は一体、どのようにDXを進めているのか。
元政府CIO補佐官で、一般社団法人CIOシェアリング協議会副代表理事などを務める坂本俊輔氏と、システム構築を担う三菱電機インフォメーションネットワーク(MIND)を交え、JAFの DXの全貌を聞いた。
INDEX
- DXの成功のカギは戦略やおカネじゃない
- 人材育成から着手したJAF
- 「2025年の崖」対応から始まったプロジェクト
- 堅実さで選んだパートナー
- 全職員3500人にITリテラシーとガバナンスを教育
- データHUBを起点に会員のワクワクを創る
DXの成功のカギは戦略やおカネじゃない
──まず坂本さんにお聞きしたいのですが、日本のDXは他の先進国に比べて遅れていると聞きます。どのような背景があるのでしょうか。
坂本:欧米に比べて日本の企業は、社内にテクノロジー人材が少なくシステムを内製する力が弱いといわれています。何か新しいシステムが必要になった時、ITベンダーに安易に丸投げしているケースが少なくありません。これでは、社内に人材が乏しいのは当然です。
これまでのメインのIT投資分野だった、既存業務の効率化やコスト削減であれば、外部のITベンダーにも丸投げしやすかったですが、DXはそうはいきません。DXとは単純なデジタル化ではなく、テクノロジーを活用した変革のこと。
事業そのものを理解していないと取り組めないものですから、外部のITベンダーと組むのはいいですが、リードするのは事業会社、ユーザー企業です。それなのに、最適な人がいないからDXが進まない……。DXの取り組みが遅い大きな理由は、戦略が雑とかおカネが足りないとか、そういうことではなくて人であると私は思っています。
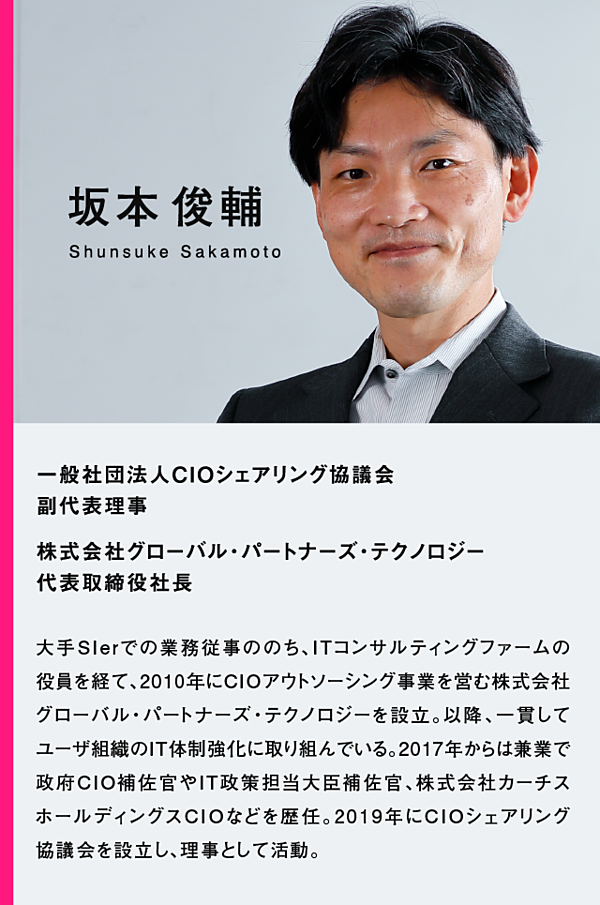
加えて、私がもう一つお伝えしたいのは、テクノロジー人材とはIT部門やDX担当部門の人だけを指すわけではないということです。
──どういうことか、具体的に教えてください。
坂本:今やどの仕事であってもテクノロジーを使わない仕事はありませんよね。であれば、全ビジネスパーソンがテクノロジーの知見を深めるべきだと思っています。
なにも、プログラムを書けるようになれとか、高度なデータ解析ができるようになれとかそういうレベルではありません。ある仕事やプロジェクトを任され、どうやってクオリティ高く効率的に進められるかを考える時に、どんなテクノロジーを活用すればいいかを想像できるようになってほしいです。
DXはIT部門に任せておけばいい話ではなくて、自分自身に関わることだと認識を変えていくことが、最も大切なことです。
今は、ローコード/ノーコードツールの普及によって、少し勉強すれば誰でもアプリケーションが作れる時代でもあります。なので、社員のテクノロジーに対する意識、見識が高まれば高まるほどDXのスピードは一気に早まると思います。
DXの本質とは全社員のキャリアにテクノロジーを組み込むということだと思っています。
人材育成から着手したJAF
──JAFは2020年にDX推進本部を設置し、DXの取り組みを加速させているとお聞きしています。そのトップを廣野さんが務めています。
廣野:DX推進本部は、2020年4月にシステム部を改組して生まれ、現在39人が在籍しています。DXに向けた本格的な取り組みは、私がシステム部長に着任した2019年から開始しました。
最初に着手したのは、坂本さんもご指摘されている人材育成と、組織づくりです。元がシステム部なのでエンジニアが母体になっていますが、私はそれだけでなくさまざまな事業部門の人間も巻き込みたくて、DX推進本部の設置にあたり、全職員を対象にDX推進人材を社内公募しました。
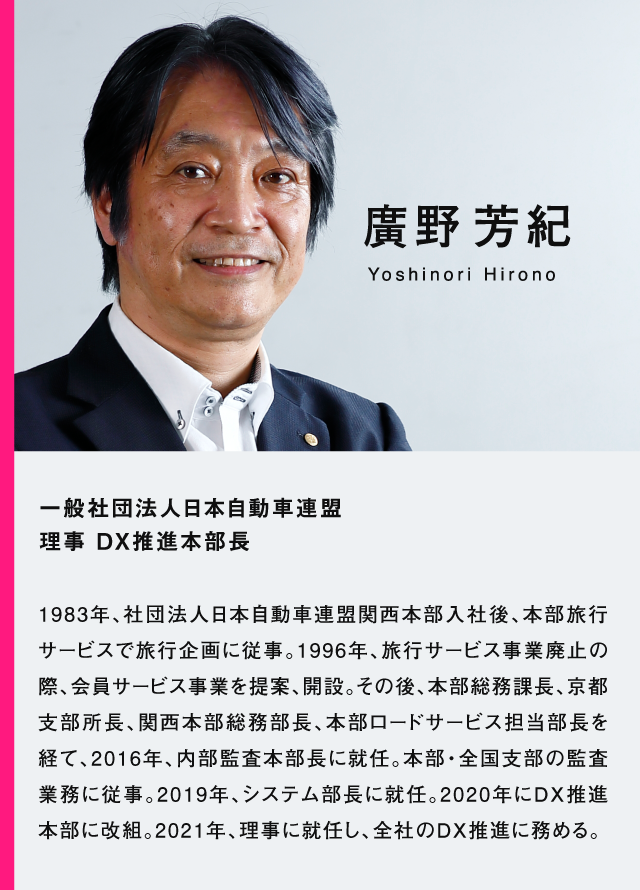
──どんな狙いがあったのですか。
廣野:1つ目は、テクノロジーを活用するのは現場の人ですから、現場の声を生かしたかったこと。実は、私自身、前の担当業務は内部監査で、決してテクノロジーに明るいとはいえません。ですが、だからこそ、現場がテクノロジーで解決したいことが分かる。公募採用にこだわったのも、私がテクノロジー畑の人材でなかったからかもしれません。
2つ目は、DXを全社的なムーブメントにしたいからです。公募した人材は、基本的に3年ほどで事業部門に戻ることになっています。約3年で、デジタルやテクノロジーのノウハウを得た人材が現場に戻り、その人がアンバサダーとなって各部門のDXを推進する。そうして、みんながDXを自分ごと化できる。そういった波を期待しています。
──なるほど。面白いですね。
坂本:いいですね。先ほど私が伝えたように、全メンバーにテクノロジーの知見を深めてもらうという意味で、すごく良い動き方だと思います。
廣野:公募がどれだけ集まるか読めなかったのですが、これが予想以上に集まって。また、集めたからどう動かしていこうと思っていましたが、みんな自発的にこの業務には、このテクノロジーは使えないかを議論して、試行錯誤しながら前に進めてくれています。
ハッカソンにも積極的に参加して、いきなり賞を受賞してきたこともあって。最初はどうなるか未知数でしたが、うまく滑り出してくれたなと思っています。
「2025年の崖」対応から始まったプロジェクト
──DX推進本部が推進しているビッグプロジェクトとして新たなシステム構築も行っていると聞いています。具体的な内容を教えてください。
廣野:先ほどお話ししましたが、私は監査本部からの異動で、そもそもテクノロジーに詳しいわけではありませんでした。システム部長に着任してまず色々な課題の把握をしている中で、経済産業省が指摘する「2025年の崖」がJAFにもあるのか調べることにしました。
──2025年にシステムの保守期限が一斉に訪れ、その更新対応がDXの妨げになるという指摘ですね。
廣野:自分たちが管理するバックオフィス系のシステムが、2023年にリプレースしなければならないことが分かったのです。対策を考える中で、既存システムと同じようなものに更新すべきではないと考えました。
その背景には、JAFのシステムは会員が望んでいるサービスを提供できているのかという課題意識がありました。JAFは2000万人以上ものお客様がいて、プライベートでもビジネスでもお客様に安全で快適なクルマ社会と安心のロードサービスを提供していくため、今後はデータを活用したよりよいサービスを作る必要がある。だから、JAF全体のシステムも大幅に見直す必要があると考えました。

JAFは2000万人以上の会員の快適なドライブを日々サポートしている(写真提供:JAF)
これまでシステム部が主に管理するのはバックオフィス系のみで、フロント系は各事業部門が独自に導入・運営してきました。そうすると、システムはサイロ化し、システム外のデータを活用したくても容易に取り出せない状況にありました。
坂本:なるほど。このような分断は日本企業の多くが抱える課題ですよね。同じ企業に属していても、部門によって思惑は異なる。管理を各々に任せれば、当然システムはサイロ化、複雑化して、全社的なプロジェクトを横軸で行おうとしても、システムがそれを阻むということは結構多いんです。
廣野:JAFもそういう状態でした。そこで、フロントのシステムと更改を控えていた基幹システムを融合することにしました。データの収集、連携、分析を1つの基盤で実現し、基幹システムや各フロントシステムとハブのように疎結合する「データHUB」を構築するための「データHUBプロジェクト」を開始しました。
併せて、フロントにある非デジタルの業務については、できるかぎりデジタル化を進めることにより、手作業を減らし、本来すべき企画などの業務に集中できる環境づくりも並行して行いました。
堅実さで選んだパートナー
──データHUBの構築には、三菱電機インフォメーションネットワーク(MIND)が携わりました。これまで接点がなかったと聞いていますが、馴染みのあるシステム開発会社のほうが安心だったのではないですか。
廣野:そうかもしれませんが、データHUBのコンセプトを実現できることを重要視しました。データ活用に適したシステム構成の知識がなかったものですから、データ活用基盤の構築に実績のある会社を中心にプレゼンを依頼し、最終的にMINDを選びました。
──なぜMINDだったのでしょうか。
廣野:他社に比べると、プレゼンの内容が堅実でした。JAFがサービス提供する会員の数は非常に多いですから、それを支えるシステムもスケールの大きい提案が多かった中、MINDは実績のあるスモールスタート可能な構成を提案。技術進歩のスピードも見越して、最初から全部決めて大規模な機能やシステムを実装するのではなくて、まずはしっかりした基盤を構築し、周辺は後から最適なものを取り入れようという発想でした。
データ活用は初心者です。自動車に例えるなら、いきなりフル装備の高級車は乗りこなせません。まずはシンプルな装備の大衆車から始めて、状況を見極めながら徐々に装備を拡充していくべきだと考えました。
鈴木:MINDはデータ活用に適したさまざまな提案のバリエーションを持ち合わせていますが、今回は基幹システムが含まれていますから、安定性や実績ある構成にすることを念頭に置いて提案しました。
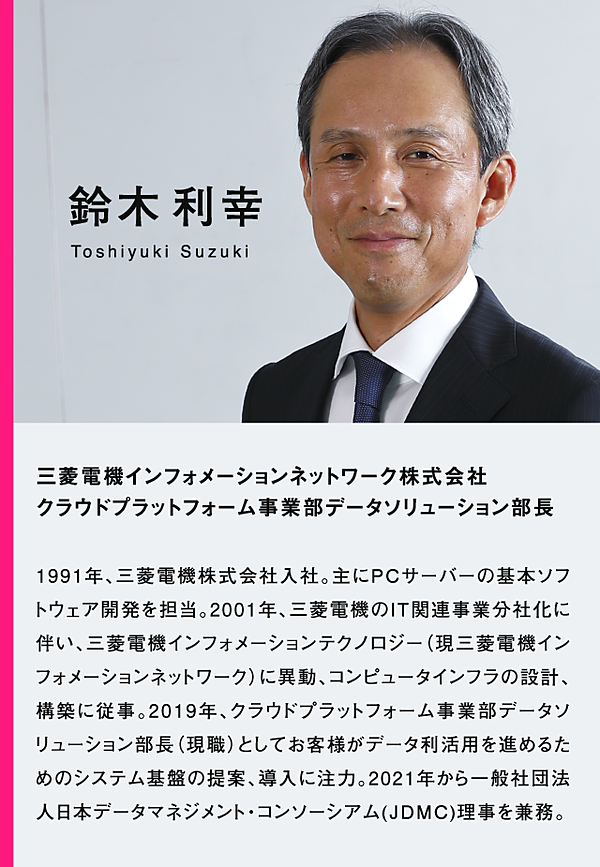
坂本:昔は巨大な統合システムが好まれて選ばれました。しかし、そうした密結合のシステムはビジネスの変化に弱く、システムが足かせになってビジネスを変えられなくなる本末転倒の事態に陥りかねません。
DXは、デジタルを使ってビジネスを変えるビジネストランスフォーメーションですので、データHUBプロジェクトが目指したような、個別に築いたシステムのデータが有機的につながり、領域ごとに柔軟に変更していけるシステムは理想的ですね。

鈴木:プロジェクトのはじめに廣野さんと話してみると、改めて廣野さんのDX推進にかける本気度をひしひしと感じました。システム統合の一環でのデータ活用や、ITをさらに効率的にすることだけを目指しているのではなく、新しいJAFのビジネスを創造するための基盤を作りあげようとしているのだ、と。
もう一つJAFの素晴らしさで紹介したいのは、データHUBを使いこなせる組織づくりや教育にも熱心に取り組んでいらっしゃることです。
全職員3500人にITリテラシーとガバナンスを教育
──JAFで実施した教育についても教えてください。
廣野:これからDXを進めていくうえで、全職員のITリテラシーのレベルを一緒にしようと考えました。そうしないとDXのゴールが人によって違ってきますし、システムに期待するばかりになってしまうことを危惧したのです。そうではなく、ツールとして使っていくものだという意識を植え付けないと、データを最大限に活用できません。
そしてもう一つ、フロントの会員情報を扱うのですから、ガバナンスは意識しなければなりません。そこで併せて、全職員のITガバナンス教育も行いました。
教育の方法は、若手の発案をもとに「JAF IT アカデミー」と名付けたプロジェクトを立ち上げて実施。最終的には全職員3500人が修了しました。

坂本:この規模での取り組みは初めて聞きました。ITリテラシーやデータリテラシーは、社会人として当たり前に必要なものになってきています。ITリテラシーは特定部門だけのものでなく、一般常識であることを企業は浸透させなければなりません。それをJAFは見事に実現していますね。
データHUBを起点に会員のワクワクを創る
──データHUBはまだ進化の途上かと思います。このようなシステム構成の場合、今後何に注意すべきでしょうか。
坂本:これから本格的にデータHUBを通じたデータ連携を進めていくと、データの中身が同じなのに項目名は違う、同じ住所なのに異なる形式で登録されているなど、細かなことですが重要なデータ整備がしばらく続くことが想定されます。
横断的なデータ活用の実現は、こうした地味な活動がとても重要ですから、我慢強く進めてもらえればと思います。MINDは、単なるデータ形式の変換屋にとどまるのではなく、データマネジメントのビジネスパートナーとして、データの標準化の推進にも貢献いただければと思います。
鈴木:MINDとしてもそのつらさは熟知しておりますので、データマネジメントチームを組織し、マスタデータ管理や標準化の仕組みを取り入れるなどしてサポートしていきます。

廣野:JAFでは、自動車メーカーや販売店、全国の自治体、観光施設などとも連携をとって、さまざまな情報を収集できる体制があります。JAFだけのデータだけでなく、他社とも協力してロードサービスを超えたお客様のカーライフ体験の向上に総合的につながるデータ基盤を作っていければと思っています。
JAFが求められている本来業務を突き詰めると、クルマの故障・トラブルになったときに助けてくれるロードサービスではなく、クルマの故障・トラブルなく、安全で安心にドライブを楽しめるさまざまなサービスを提供するということ。
将来、故障を予測してサービス提供できるようにできれば理想的です。JAFの会員になるとワクワクするね、と言っていただけるさまざまなサービスを作っていければと思っています。そのため、データ利活用はJAFのDXに最重要な手段だと思っています。
(執筆:加藤学宏 撮影:竹井俊晴 デザイン:小谷玖美 取材・編集:木村剛士)
※所属部署・役職は2021年10月取材当時のものです。