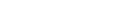Vol.33
松井孝典先生のこと
なぜ地球は生命あふれる惑星になったのだろうか。
僕はそのからくりを知りたい。そして、できることなら、地球のような惑星が宇宙でどのくらいありふれた存在か—その普遍性を知りたい。
古代ギリシャや中国の思想家の例をあげるまでもなく、ものごとの普遍性を探り求めたいという欲求は学問の原点であり、人間固有の感情である。
僕が、地球と生命の普遍性というものの考え方について、初めて気づかされたのは高校2年生のときだった。“気づかされた”と書く通り、自発的にこのようなことを想起できるわけはなく、ある一般書がきっかけであった。
それは『地球・46億年の孤独』という本であり、著者は、当時東大の助教授をしていた松井孝典先生であった。
多くの高校生にとって、進路の選択は直近の大問題である。理科系科目が好きだった僕は、物理・化学・生物・地学から何を大学で選ぶかという選択の助けになればという程度の軽い気持ちで、この本を手に取った。
それが僕のその後の人生を半ば決定した。
地球とはいかなる惑星なのか、なぜ生命はそこに誕生して進化しえたのか、人類の存在理由とは何なのか。当時全く考えもしなかった—しかし誰しもの潜在意識のなかでふつふつと地下のマグマのように胎動している根源的な数々の問い。
これらの問いに答えるには、当然のごとく、物理・化学・生物・地学といった知見を統合せねばならない。本を読み、諸学の統合の上に屹立する新しい「地球観」に触れた気がした。
同時に大学で何の学問を選択するかという考えは僕から消え去り、大袈裟に言うのならば、どういった世界観に触れたいかという点で、自分の行先を考えるようになった。
当時の僕の学力からすれば、東大など雲の上の上のさらに上であったが、1日十数時間を勉強時間に充て何とか合格し、地球惑星物理学科にも進学できた。
大学院入試で、松井先生を訪ねて、研究室所属の希望を伝えたところ、返す刀で「ところで、君は博士課程まで進むつもり?」と聞かれた。科学者を志し、博士課程に進む心積もりではいたが、とっさのことに条件反射的に「はい」という言葉が口から出た。「そう。博士まで行かないなら、婉曲に断ろうと思ったんだが。まあ、そういうことなら受け入れるよ。」
そこから僕の研究人生が始まった。
水蒸気大気と水惑星
修士課程に入った僕は、原始地球で起きる小天体の衝突と、それに伴う化学反応を研究した。天体の衝突は一般的には物理過程として理解されていた。そこに化学の要素を導入する点が、当時新しかった。天体衝突でおきる反応で、生命の材料が生まれるかという問題に没頭した。

松井先生ご本人も東大の最終講義で述べておられたことだが、先生の研究史を3つの段階に分けるとすれば、1970年代の月と地球の起源の探求を第1期、1980年代の地球の大気と海の誕生の探求を第2期、そして、1990~2000年代の生命の起源と進化の探求を第3期と大分できる。僕が研究室の門をくぐった時期は、ちょうど第3期である。
第1期にあたる1970年代では、アポロ計画によって月の誕生直後の状態が明らかになり、それに伴って原始地球の描像が刷新されつつあった。月も地球も低温の岩石のかたまりから始まったというのがアポロ以前の常識であったが、ドロドロに融けたマグマの海を持つ高温の天体として始まったことが、月試料でわかってきたのである。
しかし、なぜ月や地球は高温になりえたのか—その理論的な説明は当時なかった。松井先生は、原始太陽系に存在した無数の小天体の衝突の重要性を指摘した。天体衝突によって原始地球が成長するだけでなく、その熱で地表にマグマの海ができることを示したのである。
当時、アポロ計画に触発され研究する日本人はほとんどいなかった。当時の日本には、地球の地震学や測地学はあり、また一方望遠鏡で星を眺める天文学はあった。しかし、月や惑星は、既存のどの分野にもはまらなかった。大御所と呼ばれる先生も—あるいは既存分野の大御所であるがゆえに—未開の領域である月や惑星には手を出さなかった。そのため松井先生は、大学院生でありながら、日本における惑星科学の第一人者となってしまった。

第2期にあたる1980年代では、第1期に確立した地球誕生のシナリオに基づいて、大気や海の起源を考えた。松井先生は、衝突する無数の小天体にごく少量含まれていた水分や炭素が、高温のためガス化して原始の水蒸気大気ができたという考えを提案した。この考えを検証するためには、隕石学、気候学、大気科学、岩石マグマ学といった知見を統合する必要があった。
小天体に含まれる水分は、原始地球で蒸発し水蒸気大気を作る。水蒸気はマグマの海にもよく溶ける。水蒸気が大量に大気に放出されると、その温室効果で表面温度が上がり、マグマの海が一層広がる。すると、その広がったマグマの海により多くの水蒸気が溶け、大気の水蒸気量が調整される。一方、水蒸気の放出が少ないと、温室効果が低下して表面温度がさがり、今度はマグマの海が固化して縮小する。すると、マグマに溶けていた水蒸気が固化に伴い放出され、大気の水蒸気量が調整される。
このようなフィードバック作用によって、大気中の水蒸気量が一定値に自己調整されることを、松井先生は理論的に示した。原始地球が想定されるどんな材料や形成過程でできても、ある一定量の水蒸気大気ができるという必然性を示したのである。計算された原始大気の水蒸気量は、現在の地球の海水量と符合する。その後、原始地球では、衝突する小天体が減ってくるに従い水蒸気大気が冷えて凝結し、猛烈な雨として地表に降りそそぐ。これが海の誕生である。一方で、太陽に近い金星では、水蒸気が凝結できるほど温度が下がり切らず、おそらく海は誕生できなかった。地球が水惑星になる必然性を明らかにしたと、多くの科学者がこの水蒸気大気の理論に注目した。

世界と競争せよ
月と地球の起源を研究し、大気や海の誕生を解き明かした後、ごく自然の流れで、松井先生の興味はそこでの生命の誕生と進化へと移行していく。生命の材料はどこから来たのか、生命の進化に好適な環境がいかにしてつくられたのかということが研究対象となっていく。そのために、地球化学、有機化学、堆積学、物質循環学、古気候学、古生物学といった知見を取り入れていく。僕が研究室に入ったのはそういった時期であった。
どこの大学院の研究室でも同様であろうが、研究室ではセミナーと呼ばれる内輪の発表会がある。僕が最初に参加したセミナーの発表者は松井先生だった。内容は、2001年3月にアメリカで行われたアストロバイオロジー科学会議の紹介であった。2001年当時、アストロバイオロジーというものを知っていた日本人は数えるほどしかいなかったろう。当然僕も初耳であった。
NASAは2000年に第1回のアストロバイオロジー科学会議を開いていた。2001年の第2回会議は、招待された参加者のみからなる会合だった。日本から招待されたのは2名のみであり、その1人が松井先生だった。
「生命の普遍性を宇宙に探るというのが、明らかに今度の世界的な潮流になりつつあります。皆さんの研究も当然アストロバイオロジーに含まれます。こういった世界を意識し、世界と競争しなければいけない。」と言われた。
松井先生は常に“世界と競争せよ”と言われた。大学院生でも、周囲の院生や教授の様子をうかがうのではなく、世界のトップを意識して競争しなければならない。何かの第一人者になれば、そのうねりの先頭に立つことができる。そうなれば、放っておいても、うねりに身を任せて、個としての自分の力以上のところへも進んでいけるとも言われた。
本質的に新しいこと
もう1つよく言われたことは、“本質的に新しく根源的なことを考えよ”ということである。
内輪のセミナーに限らず、松井先生は常に厳しかった。学問として妥協はなく、相手が学生だろうか、教授だろうが、その点において等しく情け容赦なかった。
あるとき大学院生の僕は、研究室のセミナーで、タイタンやガニメデといった巨大な氷衛星の内部構造の進化について、ずっと暖めておいたモデルを提案した。
今にして思えば、そのモデルは欧米の研究者が提案したモデルを、部分的に要素を足して修正したに過ぎないものであったが、先生に烈火のごとく怒られた。君のモデルの何が本質的に新しいのか、他人の二番煎じか、とこき下ろされた。
本質的に新しいアイデアはそう易々とは出てこない。どんな天才でも10年に1つ出るかどうかである。しかし、本質的に新しいことを考えだそうとする努力を止めてはならない。止めてはならないが、日常としては、実験なり解析なりの基礎的なデータを、きちんと精査して世に出すという地味なことを積み上げない限り、世界から信頼されない。二番煎じのような研究をしていてはいけない。
10年ほど後、僕がNASAカッシーニ探査のチームと共同で、土星衛星エンセラダスに関して地下海に熱水環境があることを発見できたのも、僕の出した地味な実験データを彼らが信頼してくれたからである。その土台となったのは、先生からの教えにあった。
人間とはいかなる存在か
その松井先生が、去る2023年3月22日の夜、にわかに亡くなられた。
明けて23日の朝一番に電話でそれを知った。電話を受けつつ、顔をあげられなかった。日常の仕事に対することにたえられず、その日は半ば無為に過ごした。
松井先生は、“本質的に新しく根源的なことを考えよ”と常に言われた。先生にとってそれは、「地球に生きる人間とはいかなる存在か」という問いでなかったかと思われる。
地球の起源、大気や海の起源に始まり、生命の起源と進化を経て、千葉工業大学に移られた後は、研究対象が、鉄器文明の伝播など人間と文明論にまで達した。地球の誕生から文明まで生涯をかけて行きついた、壮大な「地球観」に圧倒される。同時にこれは僕らへの大きな遺産だと思っている。
僕にとって“本質的に新しく根源的なこと”とは、「宇宙における生命」である。地球外に生命が生存可能な場所を探し、生命を予測して発見する。その過程で、なぜ地球は生命あふれる星になったのかそのからくりと、生命の普遍性を知りたいと願う。
これまで、数年に1度程度、その問いに一歩でも近づけたと思ったら、僕は先生に近況を報告した。長くお話しした最後は昨年の夏であった。すでにご病気もあったのか、今日は来てくれてどうもありがとう、と最後に先生が言われた。思えば、ありがとうと言われたのは、二十数年来、何やら初めてのような気がした。本来、感謝を述べるべきは、僕の方であったのに。
これからどう報告をしたらよいのか、今はその寂しさに耐えかねている。

- ※
本文中における会社名、商標名は、各社の商標または登録商標です。