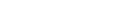Vol.60
妖怪とアストロバイオロジーV “鬼火”
今回のコラムは、妖怪とアストロバイオロジーの雑談の回としたい。これまで「天狗」、「鬼」などを取り上げ、その起源を現代科学の知見をもとに考えてきた。皆さんは妖怪を科学で説明するなど無粋と思われるかもしれないが、やはりそこには新しい発見が潜んでいる。水木しげるは、妖怪の意義を“眼にみえないことこそ大事”ということを教えてくれることだといった。妖怪を現代科学の視点でとらえたときにも、同様に意義を発見できるのである。
今回は“鬼火”を取り上げたい。
鬼火、狐火、不知火、釣瓶(つるべ)火、天火、皿数えなど、日本には数知れぬ炎にまつわる妖怪がいる。いずれも墓場や曰くつきの沼や井戸などに、夜フラフラと立ち上る火焔である。
これら火の妖怪の多くにみられる共通点として、その色が青白いことがあげられる。松明や焚火、囲炉裏の火といったように、昔の人が使う火はいずれも暖色である。一方で、鬼火は青白く、その火をみたときに昔の人が感じたであろう異様さは想像にあまりある。
面白いのは、同じような火の妖怪が、西洋にも存在することである。西洋ではウィルオウィスプと呼ばれたり、イグニス・ファトゥースと呼ばれたりする。これらは墓場や沼に夜立ち上る炎であり、やはり青白いという特徴をもつ。
つまり、墓場や沼のような場所で、青白い炎が立ち上るのは、どうやら万国共通のからくりがありそうである。もっと言えば、誰かの見間違えや目の錯覚、思い込みではなく、文化や地域、時代を超えて、複数の人間が類似の現象を目撃しており、これは科学的な意味で歴とした自然現象の観察だといえるだろう。
今回は、この怪しい青白い炎 — 鬼火について考えてみよう。

青白い「鬼火」の謎
鬼火の特徴である青白い色から、これまでも科学者たちはその正体に迫ろうとしてきた。炎の色は、何がそこで燃えているかという化学の情報を含んでいるのである。
こういうと、皆さんのなかには高校の化学で習う「炎色反応」を思い出す人もいるかもしれない。炎のなかにある元素が存在すると、その熱によってその元素は高いエネルギーを持つ。高エネルギー状態の元素はやがて元々の低エネルギー状態に落ちるが、その際にエネルギーが高い状態から低い状態へ落ちた分のエネルギーの差を、光として放出する。元素ごとにこのエネルギーの差の大きさが違うため、元素に特有の色の光が発せられるのである。
墓場や沼といった生命由来の有機物が豊富な場所では、どういった元素が青白い炎を作り出せるのであろうか。実は、これまでも大きく2つの仮説があった。
1つ目の仮説は「リン」である。リンは、DNAや細胞膜など多くの生体関連分子に含まれ、岩石や湖水に比べて、生物の体内に濃集している。生体においてリンは、リン酸という酸化物として含まれるが、生物が死ぬとその有機物を微生物が分解して、メタンなど還元的な分子を生み出す。この還元的な分子によって、生体関連分子のリン酸が還元されれば単体のリンとなりうる。単体のリンのうち「白リン」と呼ばれる結晶の発火点は44℃と低く、大気に晒されれば自然発火する。この白リンが燃えれば、淡い青色を呈するのである。
もう1つの仮説は「メタン」である。上で述べたように、生物が死ねば、その有機物はメタン菌を含む微生物によって直ちに分解されメタンが生成する。よく知られた例としては、陸に座礁して死んだクジラの体内にメタンが充満し、そのガス圧に耐えきれずにクジラ自体が爆発するように破裂することも起きる。メタンは都市ガスの主成分であり、メタンが低温で酸素とよく混じって燃焼する場合、CHやOHなどのラジカルが発光してこちらも青白い炎となる。

鬼火仮説の問題点
さて、このリンとメタン、どちらが鬼火の正体であろうか。
リン説の弱点は、実際に、白リンや他の単体リンが自然界に集まって存在していることが極めて稀なことである。あるいは、ほぼないといってもいい。たとえば、鬼火は沼でもおきる。しかし、沼の堆積物や周辺の土壌を調べても、白リンが出てくることはまずない。白リンは人間が産業的に作ることはあっても、自然のなかで勝手に生まれるにはあまりに不安定な物質なのである。鬼火として世界各地で観測されるには、白リンはあまりにも存在そのものが珍しい。
一方で、メタン説の弱点は自然発火しにくい点にある。メタンの発火点は数百℃に達する。つまり、リンと違い、メタンが大気中の酸素と反応して燃焼するには、そもそもの種火が必要である。都市ガスでは、コンロのガス出口付近で乾電池等を使って火花放電を起こす。これが種火となりメタンと酸素が燃焼する。いったん燃焼が始まれば、その反応熱が次のメタンの燃焼を引き起こすが、最初の種火を自然界でどう起こすのかが問題である。落雷や山火事が、鬼火に伴い発生していたという報告はなく、メタン説にはその発生メカニズムに重大な難がある。
このように上の2つの仮説には、どれも大きな問題点がある。そのため、大気中のプラズマ現象という新しい考えも出されたが、墓場や沼に限って起きるという鬼火の場所的な特異性を十分説明するには至っていない。
そんな中、2025年9月末、スタンフォード大学の研究チームが面白い論文を発表した。掲載誌は米国科学アカデミー紀要という、自然科学分野全般を扱うネイチャーなどに次ぐ一流総合誌である。タイトルは「鬼火の正体解明:マイクロバブル間のマイクロ放電(Unveiling ignis fatuus: Microlightning between microbubbles)」というものであった。では、この大学チームは、どのようにして「鬼火の正体」に至ったのであろうか。
“微小空間”という不思議
ここでやや遠回りの説明になることをご容赦いただきたい。同じ物質でも大きさが違うと、その性質は全く違うということを説明したいのである。身近な物質でもサイズを極端に小さくすると、新規の化学的性質が現れる — 実は、こうした物理化学現象が近年、注目を集めている。
たとえば水分子。この水分子が大量に集まれば、ご存じの通り、コップに注がれる液体の水となる。この水での分子の振る舞い、あるいは水の化学的性質はよく調べられており、また一般に広く知られてもいる。一方で、水分子が数個集まる水分子クラスターでは、大量に集まった水とは全く異なる反応性や分子の振る舞いが発現しうる。
たとえば、コップの水ではほとんど進行しない化学反応が、水分子クラスターのなかでは、驚くほど急速に進行することもある。元を正せばクラスターもただの水分子であるが、これらが引き起こす反応は、まるで重金属の触媒でも存在しているかのようである。触媒なしでも驚異的に反応を進める媒体として、水分子クラスターはグリーンケミストリーと呼ばれる環境負荷の低い化学製造として活かされようとしている。
同様にサイズが小さくなると驚異の特性を示すものとして、マイクロバブルという文字通りの微小な気泡がある。通常の大きさの気泡 —炭酸飲料の泡のような— は、水中を浮上するだけである。しかし、大きさがマイクロメートルサイズのマイクロバブルとなるとその性質が激変するという面白さがある。
何が起きるのかといえば、マイクロバブルと周辺の水の境界に負の電荷を帯びたOH(-)イオンが集まり、マイクロバブル自体が負に帯電するのである。一方、サイズの大きい通常の気泡には、この負の電荷はない。したがって、負に帯電したマイクロバブルが大きい気泡に近づくと、両者の間の電位差から微小なマイクロ放電が起きるのである。乱暴にいえば、乾燥した冬場に起きる静電気と同様と思っていい。
上記のスタンフォード大学の研究グループは、メタンのマイクロバブルが水中でマイクロ放電をすることを確かめたのである。勘のいい方はおわかりだろう。墓地や沼に生物の遺骸があれば、そこで発生したメタンはガスとなる。発生したメタンのマイクロバブルは、沼の底や土壌中の間隙水を漂う。それらが互いに接近すればマイクロ放電が起き、局所的な高温をつくり化学反応を引き起こす。ちょうど、都市ガスの種火が火花放電であるように、眼にみえないマイクロ放電が種火となってメタンが燃焼し始めるのである。これが墓場や沼地での鬼火の正体だというのが、この研究の結論である。
マイクロバブルとアストロバイオロジー
さて、このマイクロバブルと鬼火との関係であるが、多くの可能性を想起させる。水中でガスができる自然現象は、他にも多く考えられるのである。
たとえば、熱水噴出孔がある。
原始地球における熱水噴出孔は、原始生命の誕生の場ではないかといわれる。そこでは、水と岩石が高温で触れ合い、水素などのガスが生まれる。これらガスは、海底の圧力次第では気泡となる。この気泡も発生当初はマイクロバブルであったはずである。
マイクロバブルの表面は負に帯電しやすく、したがって正に帯電している有機分子を気泡の表面に電気的に集めて、気泡の形の膜状組織を作るかもしれない。また、マイクロバブルが作るマイクロ放電は、触媒がなければ起きないような化学反応さえも進行させるだろう。実際、マイクロバブルのサイズ感は、初期生命の細胞のサイズ感ともよく合っているのである。このようなマイクロバブルと生命の起源を結びつける研究は、まだ始まっていない。
鬼火、そしてマイクロバブルは、僕らの眼にみえる自然現象がすべてではないと教えてくれる。大袈裟に言うならば、無意識の自己中心的な自然観から僕らを解放してくれる。知りたいと願うものの目線に近寄らなければ、普段見ていないサイズにまで自己の視野を狭めなければ、真実は見えてこない。これこそ、“眼にみえないことこそ大事”という、水木しげるの妖怪の存在意義にも通じる、ものごと見方の本質に違いない。
- ※
本文中における会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。